 |
|
|
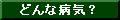 |
���@�F�m�ǂ̒�`
�@��V�I�Ȕ]�̕a�C�ɂ�萳��ɔ��B�����m�I�@�\���S�ʓI�������I�ɒቺ�����퐶���Ɏx�������Ԃƒ�`����Ă��܂��B
���@���Y��Ŕ�������邱�Ƃ�����
�@�N�����̕��Y��(������ǖY��)�ƕa�I�ȕ��Y�ꂪ����܂��B
������H�ׂ����Y���͔̂N�����̕��Y�꒩�H�ׂ����ǂ�����Y���͕̂a�I�ȕ��Y��ł��B������l�̖��O���v���o���Ȃ��͔̂N�����̕��Y���������Ƃ�Y���͕̂a�I�ȕ��Y��ł��B�Y��邱�Ƃœ��퐶���Ɏx�Ⴊ�ł�B�d�������Ă���ƋC�Â��₷�����A�ސE����l��炵�����Ă���ƋC�Â��ɂ����������x��₷���X��������܂��B
���@�A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂƂ�
�@�F�m�ǂ̌����̑啔��(�T�O��)���߂܂��B�]���Ǐ�Q���R�O���A���̑����Q�O���ł��B
�]�̐_�o�זE���ϐ��E���ł��Ă����ލs�ϐ������ł��B
�����͕s���ł����A����F�̗D����`��������̂�����܂��B
��Ǐ�͔F�m�ǂł���A���퐶���Ɏx����������܂��B
�o�߂͐i�s���ŕ��ςW�`�P�Q�N�̌o�߂ŐQ������ɂȂ�܂��B
���{�I�Ȏ��Ö@�͍��̂Ƃ��둶�݂��܂��A�����f�f�E�������Â��邱�ƂŁA�i�s��x�点����A�Ǐ���y�����邱�Ƃ͂ł��܂��B
�����ł̓A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ𒆐S�ɏq�ׂ܂��B
|
 |
�@�s���ł����A
�P�D��`�q�ُ�
�@�@�@���A�~���C�h�O��`����`�q�i�Q�P�Ԑ��F�́j�E�E�_�E���ǂƂ̊W
�@�@�A�v���Z�j�����P��`�q�i�P�S�Ԑ��F�́j�E�E�Ƒ���AD�P�O�O������
�@�@�B�v���Z�j�����Q��`�q�i�P�Ԑ��F�́j
�@�@�C�A�|���|�`���d��`�q�i�P�X�Ԑ��F�́j
�@�@�@�@E2�EE3�E�d�S �̂R�^�A�R���X�e���[���^���`���A�]���ǐ��s���Ƃ̊֘A��
�@�@�D���̑��F�P�Q�Ԑ��F�́H�A�R�Ԑ��F�́H
�Q�D���A�a�A�������Ȃǂ̐����K���a
�R�D�O��
�S�D����
�T�D���i�E�E�E�Z�ʂ̗����Ȃ������^�ʖڂȐl�E���ɓI�Ȑl
�U�D���E�E�E���I��
�V�D���̑��E�E�E�A���~�j�E���E�����E�_�E���ǂ̉Ƒ���
�Ȃǂ�����Ă��܂��B
|
 |
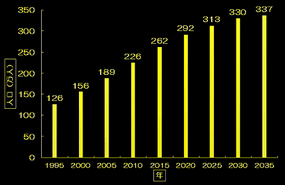
|
�@�F�m�NJ��҂����
���ݖ�Q�O�O���l�B
�����̈�r�����ǂ��Ă��܂��B |
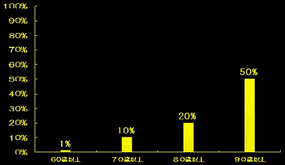
|
�@�F�m�NJ��҂����
�N��ƂƂ��ɑ������܂��B
�X�O�Έȏ�ł͂Q�l�ɂP�l�͔F�m�ǂł��B |
|
 |
���@���j�Ǐ�i�L����Q�E�F�m��Q�E�l�i�ω��Ȃǁj
�@�_�o�זE�̒E���ɂƂ��Ȃ��\�͂̑r���ł��B���x�̍��͂��ꂷ�ׂĂ̊��҂ɂ݂��܂��A�����̐i�s�ƂƂ��Ɉ������܂��B
���@���ӏǏ�i���_�Ǐ�E���s���j
�@�c������_�o�זE�̏�Q�ɑ��锽���ł��B�݂��Ȃ����҂����܂��A�����̏d�Ǔx�i�i�s�j�Ɣ�Ⴕ�܂���B
���@���j�Ǐ�̌o��
�P�D����(���Y��)�@MMSE�F20-30�_�@�P�`�R�N�@�L��(�L����)��Q�A��������Q
�Q�D����(������)�@MMSE�F10-20�_�@�Q�`�P�O�N�@����A���s�A���F�A�\����Q
�R�D����(�珰��)�@MMSE�F�O-10�_�@�W�`�P�Q�N�@�l�i����A�����A�����A�Q������A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���O���nj�Q
|
 |
���@�m�\����
�@��ɋL���͂̒ቺ���ؖ����܂��B
HDS-R(���蒷�J�쎮�ȈՒm�\�]���X�P�[��)��
MMSE(�~�j�����^���e�X�g)�Ȃǂ�����܂��B
���@�摜�f�f
�@�����̓��肨��ё������̏��O�����܂��B
����CT�EMRI�E�E�E�]�ޏk�E�]�a�]���g��ȂǁA�]�̌`�ԓI�ُ킪�����܂��B
�]����SPECT(�X�y�N�g)�E�E�E�]�����ʂ������Ă��镔���������܂��B
�����PET(�y�b�g)�E�E�E�E�u�h�E������ʂ��ቺ���Ă��镔���������܂��B
SPECT��PET��CT�EMRI�ɂĊm�F�����`�ԓI�ُ킪�o������O�̑����������\�ł��B
���@�a��
����I�F��]�̈ޏk�B�]�a�E�]���̊g�傪�����܂��B
�������I�F�V�l���̌`���A�_�o�זE�̐_�o�����ەω��A�_�o�זE��������E��ω��A�_�o�זE�̕ϐ��E���ŁA�זE�\�z�i�玿�w�\���j�̕���B�C�ȏ�ω��������܂��B
|
 |
�P�D���A�a�A�������Ȃǂ̊댯���q���R���g���[������B
�Q�D�Љ�I�Ȋ����A��A�^���𑱂���B
�R�D�����ǂ���炵�Ă������Ƒ�����͂̐l�Ƙb�������B
|
 |
���@�{�ݓ������̔F�m�NJ��҂ɐڂ����{�I�ȐS�\��
�@�܂������F�m�ǂ𗝉��������Ƃł��B�a�C���w��I�E��w�I�ɗ������Ȃ���A���̍�������P�A���ł���͂�������܂���B
�@�������҂���l�𗝉����l�i�d�������Ƃł��B���Ҍl�̐����j�E���E�����𗝉����A�l�ԂƂ��đ��d����悤�ɂ��܂��B�F�m�NJ��҂���͖����ɂȂ��Ă��v���C�h�͕ۂ���Ă��܂��B�F�m�ǂ����邩��Ƃ����Ďq���̂悤�Ɉ����̂łȂ��A�l���̐�y�Ƃ��Čh�ӂ������Đڂ���ׂ��ł��B�g�̍S���Ȃǃv���C�h��������悤�ȍs�ׂ́A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����s��Ȃ��悤�ɂ��܂��B
�@��O�������I�E��e�I�ԓx�Őڂ������Ƃł��B�F�m�NJ��҂���ɂ́A�ߋ��E���݁E�����Ƃ������ԓI�Ȃ���������Ă��邱�Ƃ������B�܂����m�ƃ��m�Ƃ̋�ԓI�Ȃ���A�l�Ɛl�̐l�ԓI�Ȃ���������Ă��邱�Ƃ������B���ԁA��ԁA�l�ԊW���|�������A���҂���Ǝ��̔��I�Ȑ��E�ɐ����Ă��܂��B���������ׂĎ���A���̎��Ԃ����ɐ�����Ƃ����ԓx����ł��B����Ō�Ƃ������̂��ƂɊ��҂���̊ԈႢ���C��������A�{�������A���ГI�E����I�w�������Č������������邱�Ƃ͕S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��ł��B����̐l�͎����̘b�������Ă���Ȃ��B�������������Ƃ��肵�Ă���B�{���Ă��肢��B�������o�J�ɂ��Ă���B��ƌ����A���҂���̐S������A����܂��܂��s����ɂ��Ă��܂��܂��B�����I�E��e�I�ȑԓx�łȂ���Ί��҂���Ɛڂ��邱�Ƃ����ł��Ȃ��ƃL���ɖ�����ׂ��ł��B
�@��l������ʂł̌𗬂��d���������Ƃł��B����̓v���C�h�ƂƂ��ɁA�F�m�ǂ��i�s���Ă��Ō�܂Ŏc���Ă�����̂ł��B�C�����̌𗬂݂̂����҂���̎c���ꂽ�Ō�̎��Ԃ�L���ɂ��܂��B�u���q���������ɗ��Ă���Ăق�Ƃ��ɂ悩�����ˁv�ȂǂƂ����Ƃ��ɂ��S�����߂Ăقق���ł����Ă��������B���҂�����Ί�ɂȂ�͂��ł��B
�@��܂ɃO���[�v���[�N��������邱�Ƃł��B�W�c�ł̃��N���[�V�������Ƃ�ʂ��ēK�Ȗ������ʂ����悤�ɗU�����܂��傤�B�����ӎ����������Ď��Ȍ���̏����A�O���[�v�̈���Ƃ��đ��݂��F�߂��Ă���Ƃ��������S�����ƁA���҂���̏Ǐ��肵�܂��B
�@��Z�ɐ������d�����邱�Ƃł��B�{�݂���߂����ۂŗ���閈���ł́A���̐����b����B����������܂���B�l�ԂƂ��Ăӂ��킵���A���������Ƃ�������̂��鐶���������悤�ɂ��Ă��������ƂɍH�v���Â炵�Ă��������B
�@�Ō�A�掵�����x�ȗՏ����H���s���Ă��鎩�o�E�g�������������Ƃł��B�F�m�NJ��҂���Ƃ̊W�͂����Ƃ�����l�ԊW�ł��B�܂����Â��Ă����P�������߂Ȃ����Ƃ̕��������B����ێ����ŏI�ڕW�B�����ڂ̑O�Ɏ��������Ă��邱�Ƃ������B�ł������Ƃ�����Ȏd���Ŋ��҂���̎c���ꂽ�Ō�̎��Ԃ��L���Ȃ��̂ɂȂ�̂ł��B�����l����A�X�g���X������͂��ł��B
���@�{�݂ɂ�����F�m�NJ��҂̃P�A�E���̎���
�P�D���P�A
�@�@�@�@�o���A�t���[���𐮂����퐶���ł̎��̂�h�~����
�@�@�@�@�e���̂�����A�Â����A�L���A���Ə����A�����Ȃǂ𐮂���
�Q�D�g�̓I�P�A
�@�@�@�@���ȓI�P�A�c�����ǁE�E���E�h�{�s�ǁE�S�@�\�ቺ�Ȃ�
�@�@�@�@�O�ȓI�P�A�c��ጂȂ�
�@�@�@�@���P�A�@�c�����E���֑�Ȃǁ@
�@�@�@�@���n�r���e�[�V�����c���w�Ö@�E��ƗÖ@�Ȃ�
�R�D���_�I�P�A
�@�@�@�@�v�����̂��鐺����
�@�@�@�@�W�c�Ö@�E��ƗÖ@�E���N���G�[�V�����Ö@
�@�@�@�@�@�@�@�@�����b�����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�����������������S������
�@�@�@�@�@�@�@�@���͂Ƃ̊ւ��̒��Ō������Љ������
�S�D���s���ւ̑Ή�
�@�@�@�@�������͂��ׂĎ���A���R��T��������͂���
�@�@�@�@��������ȏꍇ�̂ݖÖ@�����p����
|
 ���Ȃ̂s�n�o�ɖ߂� ���Ȃ̂s�n�o�ɖ߂� |
|
|