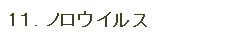 |
|
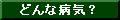 |
ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、おう吐、下痢、腹痛などを起こす感染性胃腸炎(注)です。37〜38℃の発熱がみられることもあります。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化することがあります。
ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。
(注)「感染性胃腸炎とノロウイルス」について
ノロウイルスは、「感染性胃腸炎」の原因となるウイルスですが、感染性胃腸炎の病原体には、細菌、ウイルス、寄生虫があります。原因となる病原体のうち、細菌には、サルモネラ、カンピロバクター、エルシニア、病原性大腸菌、腸炎ビブリオがあり、ウイルスは、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、アストロウイルスそしてノロウイルスがあります。
|
 |
ノロウイルスは経口感染であることははっきりしていますが、その感染経路として
(1) 患者のノロウイルスが大量に含まれるふん便や吐ぶつから人の手などを介して二次感染
(2) 家庭や共同生活施設などヒト同士の接触する機会が多いところでヒトからヒトへ飛沫感染
(3) 食品取扱者(食品の製造に従事する者、飲食店における調理従事者、家庭で調理を行う者など)が感染しており、その者を介して汚染した食品を食べて感染
(4) 汚染されていた二枚貝を、生あるいは十分に加熱調理しないで食べて感染
(5) ノロウイルスに汚染された井戸水や簡易水道を消毒不十分で摂取して感染
などがあります。
特に、(3)のように食品取扱者を介してウイルスに汚染された食品を原因とする事例が、近年増加傾向にあります。
また、ノロウイルスは(3)、(4)、(5)のように食品や水を介した直接の感染(一次感染)ばかりでなく、(1)、(2)のようにウイルス性胃腸炎(感染症)そのものが感染の原因にもなります(二次感染)。この多彩な感染経路がノロウイルスの制御を困難なものにしています。
では、ノロウイルス食中毒の原因となる食品はなにか?と問われれば、
食品から直接ウイルスを検出することは難しく、食中毒事例のうちでも約7割では原因食品が特定できていません。その中には、上で述べたようにウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたことが原因となっているケースも多いとされています。
はっきりとした原因として注目されているものとして、ノロウイルスに汚染された二枚貝(カキ、シジミ、アサリ、ハマグリなど)があります。二枚貝は大量の海水を取り込み、プランクトンなどのエサを「えら」でこしとって体内に残し、出水管から排水していますが、海水中のウイルスも同様のメカニズムで取り込まれ「えら」に濃縮して存在するためと考えられています。東京、大阪などの大都市近郊の海では生活用水が多量に流れ込むため、二枚貝のウイルス汚染が深刻です。なお、汚染されたものでも十分に加熱すれば、食べても問題ありませんが、調理した器具の洗浄が不十分で他の食品の調理にそのまま用いた場合、食材を洗った水滴などが野菜についた場合、調理した後の手洗いが不十分で他の食品に不着する場合などがあります。またパック詰食材のドリップ液にも注意して下さい。
|
 |
潜伏期間(感染から発症までの時間)は24〜48時間で、主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛です。37〜38℃の発熱がみられることもあります。通常、これら症状が3〜4日続いた後、治癒し、後遺症もありません。
|
 |
診断は、病歴と症状と診察所見から臨床的に行います。
申し出があれは、便を検体にしてRT-PCR法、ELISA法などで診断します。ふん便には通常大量のウイルスが排泄されるので、比較的容易にウイルスを検出することができます。 ただし保険適応がないため外来での検査は実費(約2万円)になります。東京などの大都市では毎年大量発生し保険を認めていたら医療経済的にたいへんなことになるということもありますし、またノロウイルスに特効薬がありませんので検査をしてもその後の治療に影響しないからのようです。風邪にかかって、どんな種類の風邪かを調べないことと同じといえます。
|
 |
現在、このウイルスに効果のある抗ウイルス剤(注)はありません。このため、対症療法が行われます。特に、体力の弱い乳幼児、高齢者は、脱水症状を起こしたり、体力を消耗したりしないように、水分と栄養の補給を充分に行いましょう。ポカリスエットなど電解質を含んだスポーツドリンクを電子レンジなどで人肌に温めたものがいいでしょう。また、一度に多くの水分や過剰に水分を取るのではなく、少量を複数回に分けてとるようにします。脱水症状がひどい場合には病院で輸液を行うなどの治療が必要になります。
止しゃ薬(いわゆる下痢止め薬)は、病気の回復を遅らせることがあるともいわれますが脱水状態をコントロールする上で有利になる場合もありますので医師の指示に従って服用してください。
(注)ウイルスの研究には動物培養細胞でウイルスを増殖させるのですが、ノロウイルスについてはまだその増殖方法が見つかっていません。そのため研究はもちろんのこと、検査や治療方法などが、他のウイルスに比べかなり遅れているようです。
また、ノロウイルスの自己免疫力は、感染者で1〜2年で失われるといわれていますので、ワクチン予防も期待できないようです。
|
 |
ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。
従って、予防対策が大切です。
食品を介した感染で最も多いのは貝類による感染で、ウイルスに汚染された二枚貝を生、あるいは加熱が不完全なままで食べることにより感染します。
ウイルスは熱を加えると死滅するので、ウイルスに汚染されている可能性のある食品は、中心部までよく加熱してください。
食品の中心温度85度以上で1分間以上の加熱を行えば、感染性はなくなるとされています。ただし、調理した器具の洗浄が不十分で他の食品の調理にそのまま用いた場合、食材を洗った水滴などが野菜についた場合、調理した後の手洗いが不十分で他の食品に不着する場合などがあります。またパック詰食材のドリップ液にも注意して下さい。
患者のふん便や吐ぶつには大量のウイルスが一週間〜一ヶ月くらいにわたって排出されるので、
(1) トイレの後や食事・調理の前などには、必ず石けんと流水で手を洗いましょう。石けんそのものにウイルスを殺す働きはありませんがタンパク質の汚れとともにウイルスを洗い落とします。
(2) 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。 ノロウイルスに感染した場合、症状が治まった後でも、一週間〜一ヶ月くらい便にウイルスがいますので気をつけましょう。調理師などは約一ヶ月の休職が望ましい。
(3) 胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。 使い捨てのガウン(エプロン)、マスクを着用し、便や吐物を直接、素手で触らず、ビニール手袋を使用してください。汚物の消毒は市販の塩素系消毒剤(漂白剤)を希釈したものを使用してください。中性洗剤やアルコールは無効です。
|
 |
厚生労働省では平成9年からノロウイルスによる食中毒については、小型球形ウイルス食中毒として集計してきましたが、平成15年8月29日に食品衛生法施行規則を改正し、現在はノロウイルス食中毒として統一し、集計しています。
平成18年の食中毒発生状況によると、ノロウイルスによる食中毒は、事件数では、総事件数1,491件のうち499件(33.5%)、患者数では総患者数39,026名のうち27,616名(71.0%)となっています。病因物質別にみると、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ(645件)に次いで発生件数が多く、患者数では第1位となっています。
過去6年間の発生状況は次のとおりです。
|
| 年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
平成17年 |
平成18年 |
| 事件数(件) |
269 |
268 |
278 |
277 |
274 |
499 |
| 患者数(人) |
7,358 |
7,961 |
10,603 |
12,537 |
8,727 |
27,616 |
|
なお、ノロウイルスによる食中毒の報告数は増加傾向にありますが、この理由としては、ノロウイルス食中毒自体の増加のほか、検査法の改善やノロウイルスに対する知識の浸透による報告割合の向上が考えられます。
|
 内視鏡のTOPに戻る 内視鏡のTOPに戻る
|