 |
|
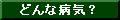 |
一般的には、三日以上にわたって排便がない状態を便秘とすることが多いのですが、個人差があるので、便秘を定義するのは容易でないとされています。排便間隔が延長(健常人では1日1回)し、糞便量が少なく(健常人では150g程度)、便が硬く兎糞状となるなどし、そのため排便時間が長い、残便感があり爽快感がなく、腹痛、腹部膨満感がある状態です。
|
 |
便秘の原因は多岐にわたり、分類もさまざまです。
便秘の発症経過から急性と慢性に分けられます。次に器質的原因疾患の有無から器質的なものと機能的なものに分けられます。器質的便秘はHirschsprung病、大腸癌、炎症、腸閉塞、腸管癒着、術後腸管吻合部狭窄、S状結腸過長症などの器質的疾患が原因となるもので、治療は原疾患に向けられます。代謝異常、心不全、感染症など全身性疾患に伴う便秘には、原疾患の治療とともに症状に応じて下剤などを必要とします。各種疾患に使用される薬剤(向精神薬、胃腸薬、抗コリン薬、アヘンアルカロイド、降圧薬など)の中には副作用として便秘(医原性)をきたすものが多です。機能性便秘には大腸の運動の低下による①弛緩性便秘(単純性便秘、常習性便秘)と、②緊張運動亢進によるけいれん性便秘(過敏性腸症候群の便秘型)と③直腸性便秘(排便困難症)に分けられます。
①弛緩性便秘では、大腸の緊張が低下し、蠕動運動が減弱して腸内容の通過が遅くなり、水分が吸収されて糞便は硬くなる。腹痛より腹部膨満が主症状となり、便意は少なく、直腸内に糞便が送られても排便反射が起こらりません。
②けいれん性便秘では、下部大腸にけいれん性収縮が生じて糞便の通過が障害される。腹痛を伴い、便意はさまざまで、便は兎糞状で少なく、排便はスムーズでなく、残便感を訴えます。
③直腸性便秘では、糞便が直腸へ入ると生じるはずの排便反射が抑制されているため排便困難となります。便意を意識的にこらえることが原因となりやすいとされています。これら便秘のうち実際の日常治療の対象となるものは慢性(機能性)便秘です。急性の機能性便秘は生活環境の変化、精神的原因による一過性単純便秘であり、下剤または浣腸などを用います。
|
 |
排便習慣を中心とした丁寧な問診により、排便の状態、便秘の期間、腹部症状、他疾患の有無、服薬状況などを明らかにします。何よりも器質性疾患の除外を行うため注腸X線検査や全大腸内視鏡を実施し、機能性であることを確かめます。器質的な病変の存在が認められる場合、あるいは神経、内分泌、代謝性疾患、膠原病などの全身性疾患の一部分症としてみられる症候性便秘の場合は、原因疾患の治療が先決です。抗コリン薬、制酸薬、整腸薬、消化酵素薬、抗生物質、アヘンアルカロイド薬、降圧利尿薬などは便秘をきたす場合があり、薬剤の変更ないしは減量が必要となることがあります。その後型別に薬剤の作用機序を考慮しながら治療方針を立てます。
■ 生活習慣の改善
生活習慣の乱れは便秘の最大の原因のひとつです。規則正しい生活を送り、十分な休養と睡眠と栄養をとり、ストレスをためないよう心がけましょう。排便をがまんしないようにすること、朝食後の排便習慣をつけさせることが必要です。
■ 運動療法
適度な運動をすることで、血液の循環がよくなり、胃腸などの消化器官の働きを活発にすることができます。日頃から腹筋を鍛えておくことは老人や経産婦など腹筋が減弱している場合に有効です。
■ 食事療法
バランスのとれた健康的な食事を、三食しっかりととりましょう。 特に朝食を抜かずにきちんと食べる習慣をつけましょう。そうすることで、胃腸、ひいては体全体がよいリズムを取り戻します。さらに、食物繊維を多く含んだ食品(注)を積極的に摂取しましょう。食物繊維は、便のかさを増やしたり腸を刺激して便意を促進させる働きがあります。消化のよい残渣の少ない食事では弛緩性便秘になりやすい。これとは逆に、けいれん性便秘では消化のよい低残渣食が有効です。また、水分を意識的にとるよう心がけましょう。便秘の人は水分が不足していることが多く、水分の摂取不足が便秘の原因になっていることも少なくありません。健康な成人の便では組成物の約8割が水分ですが、便秘の人の便は水分の割合が低く、そのために便が硬くなって出にくくなっている場合があります。起床時に冷たい水を飲むことも効果的です。
(注)食物繊維を多く含む食物:野菜、果物、芋類、海草類、糸引き納豆、おから、インゲン豆、とうもろこし など
■ 薬物療法
薬剤療法は、生活指導と食事療法の後に行う補助的な治療です。また、薬剤の選択として作用の弱いものから始め、また、同一薬剤による習慣性に注意します。下剤は臨床的に作用別に機械的下剤(塩類下剤、膨張性下剤、浸潤性下剤)、刺激性下剤、自律神経性下剤、および漢方薬、その他の下剤に分けるのが実際的です。また、下剤には薬理作用が強く約2−6時間後に排便を促す峻下剤と、緩和に作用し8−12時間後で効果のある緩下剤があります。なお、薬剤の適量には個人差があり、少量より漸増しながら適量を決めます。さらに、同一薬剤による習慣性に注意します。下剤の乱用は直腸性便秘を引き起こすという逆効果を生むこともあります。
一般に弛緩性便秘(常習性便秘)は膨張性下剤、刺激性下剤がよく、けいれん性便秘には塩類下剤、膨張性下剤、浸潤性下剤のような刺激のないものがよいとされています。浣腸は必要に応じて行うもので、恒常的に安易に行うものではありません。
①弛緩性便秘
最初に、塩類下剤(酸化マグネシウム⇒、マグラックス⇒)を単独あるいは膨潤性下剤(バルコーゼ⇒)と併用することが多いです。
処方例 下記のいずれかを用います。
1)マグラックス⇒錠(250mg、または330mg) 1.2〜2.0g 分3 食後
2)バルコーゼ⇒顆粒(750mg/g) 3−9g(製剤量として) 分3
これらで効果が不十分の場合に下記3)、4)などの大腸刺激性下剤を用います。
3)ヨーデルS⇒糖衣錠(80mg) 1−3錠 分1 就寝前
4)プルゼニド⇒錠(12mg) 1−3錠 分1 就寝前
軽い便秘には最少量よりはじめ適量を決めるが、その量は患者自身にコントロールさせてもよいです。服用時水分を多くとらせる。飲用後、2−3日後に便通があることを知らせます。本剤の投与により尿が赤色を呈することがある。多少ガスの排出、腹鳴傾向があります。
5)ラキソベロン⇒液(1mL中7.5mg) 10〜30滴 分1
6)ラキソベロン⇒錠(2.5mg) 2−3錠 分1
7)アローゼン⇒ 0.5‐2g 分1‐2
処方例5)は液状滴下剤で用量の調整がしやすく、水や飲料水に混じ服用できます。
②けいれん性便秘
下剤とともに便量を増やすために繊維の多い食事をすすめます。精神的ストレスや不安感の強いときにはマイナートランキライザーを併用します。
処方例 下記のいずれか、または併用して用います。
1)セレキノン⇒錠(100mg) 3−6錠 分3、または
トランコロン⇒錠(7.5mg) 6錠 分3
2)セルシン⇒散(10mg/g) 3−4mg(成分量として) 分3
3)グランダキシン⇒細粒(100mg/g)1.5g(製剤量として)
4)ポリフル⇒錠(500mg) 3−6錠 分3
酸化マグネシウムあるいはバルコーゼ顆粒などとの併用も効果があります。
③直腸性便秘
下記のいずれかを用います。
1)新レシカルボン⇒坐薬 1回1〜2個 1日1−2回
2)テレミンソフト⇒3号坐薬(10mg) 1回1〜2個 1日1−2回
腸内の蠕動亢進作用と排便反射を刺激する薬剤です。
|
 内視鏡のTOPに戻る 内視鏡のTOPに戻る
|